top of page
検索


SDGsやCSRを推進する上で注意点としての「擬似相関」について
SIAの今井です。 データ解析、「測定」シリーズです。 経営における、ソーシャルインパクトや分析などについて興味をお持ちの方は関連記事も是非参照ください。 ・「人工知能や機械学習は社会的インパクトマネジメントをいかに前進させるか〜World Bank David...

Social Impact Act
2019年2月4日


SDGsインデックス&ダッシュボード2018と、データ整備の必要性は普遍的か
SDGsインデックス&ダッシュボード 2018 SDSN(Sustainable Development Solutions Network:持続可能な開発ソリューション・ネットワーク」)とドイツのベルテルスマン財団が共同で、「SDGsインデックス&ダッシュボード...

Social Impact Act
2018年12月7日


民間企業によるSDGsの活性化とTFCDの進展
Social Impact Actの今井です。 今回は、SDGsとTFCDの話題についてです。 民間企業によるSDGsの取り組みの活性化 GPIFの調査によると、回答企業の約6割近い企業がSDGsの取組を実施、もしくは検討している状況とのことです。...

Social Impact Act
2018年6月25日


アメリカのBreakingGroundによる社会課題の解決〜ホームレス問題〜
BreakingGround 国連人権委員会によると、世界中で約1億人のホームレスがいると推定されています。 その中で、特に深刻な都市TOP25が紹介されています。 もっとも深刻な都市として、フィリピンのマニラとされていますが(マニアは出張などで訪れてもビジネスホテル街を二...

Social Impact Act
2018年6月12日


海外のCSVや社会起業家の取り組み事例紹介〜Maji Mamas、OffGridBox、Malnutrition Matters〜
今回は、海外で社会課題をビジネスの手法を用いて解決を目指す企業事例を紹介します。 一般的にCSVと呼ばれる領域で、ビジネスを通じた社会課題の解決等とも呼ばれますが、下記の動画等参考下さい。 Maji Mamas:Mother water Maji...

Social Impact Act
2018年3月14日


コーポレートガバナンスとして、サステナブル領域が推進されることがあるのか?
コーポレートガバナンスとは? コーポレートガバナンスとは、金融庁によると、会社が、株主をはじめ 顧客・従業員・地域社会等の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを意味する、としています。 金融庁:「コーポレートガバナンス・コード原案...

Social Impact Act
2018年3月1日


アートを活用した企業研修プログラムについて〜ArtQの運営にあたり〜企業経営×アート
SIAの今井です。 現代アーティストの紹介を兼ねて、アート作品のレンタルなどを取り組みをスタートしました。アート作家にストック収入が継続的に入る仕組みの作りの一環です。 ソーシャルインパクトアクトの運営会社のライフドラムラボは、「企業内アートコンソーシアム」の事務局として活...

Social Impact Act
2018年2月17日


中小企業・自治体連携によるSDGsの可能性について関東経済産業局でシンポジウムが開催されます
関東経済産業局〜SDGsシンポジウム〜 平成30年2月15日(木曜日)13:00~16:00に関東経済産業局にて、「中小企業・自治体連携によるSDGsの可能性」が開催されます。 ご関心をお持ちの方は、参加を検討してみてはいかがでしょうか?...

Social Impact Act
2018年1月27日


アートなどの文化的活動を、どのように経済的活動と結びつけるか?
アート領域におけるCSV事業 SIAの今井です。 Social Impact ActでもCSV、社会的価値と経済的価値の共創のテーマを幾度となく取り上げてきました。 今回は社会・文化的活動である、アートの話題について。 その他商品と同様に、アート作品についても、今や画廊や百...

Social Impact Act
2018年1月12日


経済的利益と社会的利益の両立について〜CSO:Chief Sustainability Officerとは?〜
Social Impact Actの今井です。 早いもので、2017年も12月ということで、振り返りの月になりました。 今回は趣向を変えて、自身で経営している会社(ライフドラムラボ)について。 株式会社ライフドラムラボは、Life:人生を、Drum:奏でるというニュアンスで...

Social Impact Act
2017年12月5日
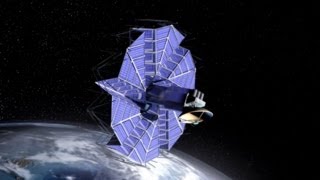
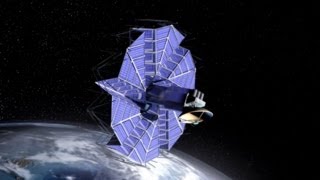
数学×折り紙〜途上国教育における折り紙の可能性について〜
数学×折り紙〜数学の力が拓く新しい折り紙の世界〜 11月22日東京ガーデンテラス紀尾井町にて、「数学×折り紙〜数学の力が拓く新しい折り紙の世界〜」が開催されました。講師は、三谷純 筑波大学システム情報系教授です。 日本人にとって折り紙は、非常に馴染み深いものではないでしょう...

Social Impact Act
2017年11月30日
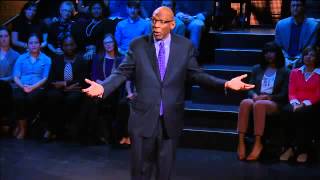
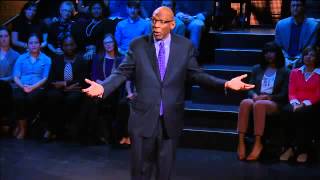
途上国向けの教育コンテンツ〜プロジェクトヒストリー「中米・算数・数学の学力向上」〜
『中米の子どもたちに算数・数学の学力向上を』 2017年11月10日にJICAにて、プロジェクトヒストリー「中米の子どもたちに算数・数学の学力向上を」が開催されました。 Socail Impact Actでは、本業の傍、有志で、途上国向け教育コンテンツを企画しており、ようや...

Social Impact Act
2017年11月20日


ソーシャルプロダクトを展示・販売する「ソーシャルスクエア」
ソーシャルスクエア/SoooooS 「SoooooS」には、フェアトレードやオーガニック、ハンドメイドや地域・伝統に根ざした商品など個性的な商品が多数掲載されています。 また、代官山に店舗を構えており、お近くに行かれた際は、立ち寄ってみてはいかがでしょうか?...

Social Impact Act
2017年10月31日


経営戦略フォーラム〜企業の競争力を高めるダイバーシティー経営〜開催されました
経営戦略フォーラム SIAの今井です。 2017年9月26日に、東洋経済にて、経営戦略フォーラム〜企業の競争力を高めるダイバーシティー経営〜が開催され、招待して頂いたため参加してきました。 時間の関係で途中で抜けてしまったので、前半部分のみとなりますが、内容を抜粋して紹介し...

Social Impact Act
2017年10月1日


2500兆円超え!?世界で急拡大“ESG投資”とは?がNHKで放送されました
ESG投資については今まで幾度となく、様々な観点から紹介してきましたが、2017年9月27日(水)のクローズアップ現代で、「2500兆円超え!?世界で急拡大“ESG投資”とは?」が放送されました。 今回はその内容を抜粋して紹介します。...

Social Impact Act
2017年9月28日


エコな中堅企業事例 中小・中堅企業のCSR 〜世紀東急工業株式会社〜
エコな中堅企業事例〜世紀東急工業株式会社〜 9月19日、港区立エコプラザで港区の事業者などを対象に、「みなとCSRアイデアソン 社会と企業の「協創」を活性化」が開催されました。 プレゼンターは、世紀東急工業株式会社さんでした。...

Social Impact Act
2017年9月25日


Social Good Summit 2017〜次の100年をつくる活動 × SDGs〜開催されました
Social Good Summit 2017 8月29日 (火)、100BANCHにて、Social Good Summit 2017 in Tokyoが開催されました。 Social Good Summitは、貧困や教育、公衆衛生、防災対策などの社会的課題の解決のために...

Social Impact Act
2017年9月7日


SDGs Insight〜企業によるSDGsの具体的活動についてインタビュー実施〜
SDGs Insightとは 国連において、グローバルな共有目標としてSDGs(持続可能な開発目標)が採択されました。 世界に目を向けると、国内外において、大小様々な社会的課題が山積しています。 その一方で、そうした課題や問題を「機会」や「チャンス」と捉え挑戦する企業や団体...

Social Impact Act
2017年9月1日


ANA SOCIAL GOODS〜社会的課題の解決に寄与するCSVマーケティング〜
CSV マーケティングとは SIAの今井です。 昨今、CSVやSDGs、ESGなどのキーワードをよく目にするようになりました。 社会課題の解決に、CSRとしてではなく、本業を通じていかに貢献すべきか?それがどう企業価値の向上や、持続可能な企業の成長というプラスのループを創造...

Social Impact Act
2017年8月29日


ユニリーバ〜アイスクリームを通じて考えるSDGsイベント〜開催されました
2017年8月25日にユニリーバ本社にて「アイスクリームを通じて考えるSDGs~SDGsゲーム体験&メーカーとしての事例紹介~」が開催されました。会社員や学生50名が参加し、SDGsゲームを体験しました。 https://www.unilever.co.jp/sust...

Social Impact Act
2017年8月26日
bottom of page
